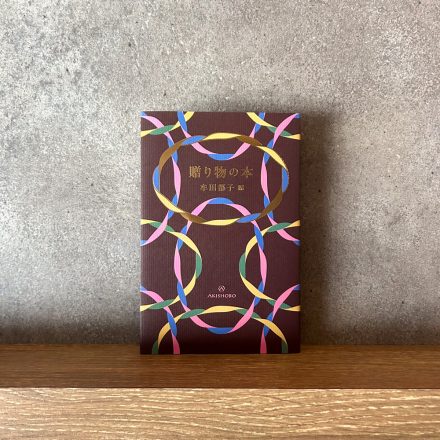『火山のふもとで』松家仁之

新潮社(2012)
舞台は建築設計事務所――語り手である主人公(坂西徹)は、大学の建築科を卒業したばかりの若者で、ゼネコンの設計部に就職することにも、当時人気だったポストモダン系の設計事務所に所属することにも違和感を感じていた。ただひとり、尊敬する建築科である村井俊輔(先生)の事務所に、新卒採用がないことを知りつつも、求職の手紙を書いて投函。そこから村井先生と所員たちとの関わりが北軽井沢の『夏の家』で始まる。
建築家である村井先生は1939年に渡米し、フランク・ロイド・ライトのもとで働いていた。『夏の家』は、ライトが設計事務所と建築を学ぶフェローシップの機能も兼ね備えた「タリアセン」の影響を受けたものと思われる。夏になると所員たちは、そこで共同生活を行いながら設計に打ち込む。建築に対する愛情や哲学が散りばめられていて、時折、村井先生の言葉に心を揺さぶられる。
《設計をするとき,火事になりにくい家,地震で崩れ落ちない家をできるかぎり心がける。それは建築家の大事な仕事だ。でもかりにだよ、東京全体が焼け野原になるような大震災があったとして、自分の家だけが燃えず崩れずでいいのか。(中略)防災をあまりに徹底した家というのは、これは要塞であって、住宅ではない。居心地がいいかどうかはなはだ怪しい。要塞に住むなんて、つねに災厄を考えながら暮らすようなものだからね》
安心・安全な暮らしを追求するあまり、快適さなどが犠牲になることに対して警鐘を鳴らす先生の言葉にはっとさせられる。
建築小説に思えるかもしれないが、基盤はラブロンス。また国立現代図書館コンペを巡る所員たちの心理や人間関係などが丁寧に描かれていたり、図書館の魅力もたくさん詰め込まれている。静謐で美しい文体が読者をどんどん引き込み、読めば読むほど好きになっていく。