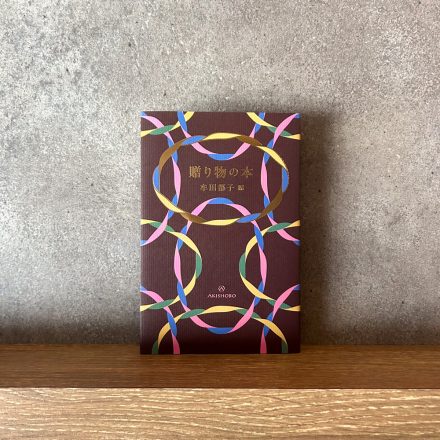ACTIVITIES
『エンド・オブ・ライフ』佐々涼子

京都で訪問医療を行っている渡辺西賀茂診療所――7年間、寄り添うように見てきた終末医療の現場が綴られている。そんな中、著者の友人でもあり、200名の患者を看取ってきた訪問看護師が癌を患い、残された日々を共に過ごし「理想の死の迎え方」を見つめ合う。看護をする立場から看護をしてもらう立場になった友人の「生きたようにしか、最期は迎えられない」の言葉が深い。また、在宅医療の取材に取り組むきっかけとなった著者の難病の母と、彼女を自宅で献身的に介護する父の話も交え、「自宅と病院」の違いや、最期を迎えるにあたり選択肢があることに気付かされる。
本書は、「Yahoo!ニュース | 本屋大賞 2020年ノンフィクション本大賞」の受賞作品である。最期を迎える人と、そこに寄り添う人たちの姿を通して、自分の死はもちろん、人の死に対しても受け入れることに目を背けてはならないと、著者が優しく語りかけてくれたような気がして涙が止まりませんでした。