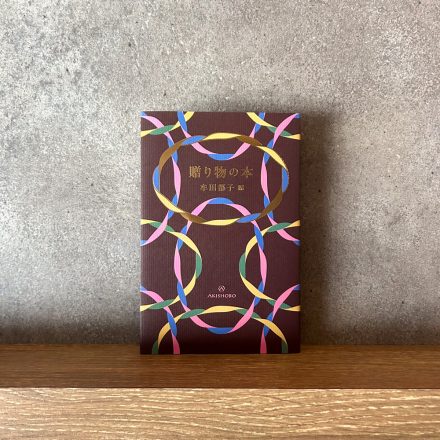『海をあげる』上間陽子

青、水色、黄色で描かれたカバー。謎解きのようなタイトル。美しい海と空を想像しながらページを繰る。しかし予想を裏切るかのように、夫の浮気、破綻した結婚と著者が経験した胸懐が一人称視点で語られ始める。静かな情景と印象的なせりふで読者を引き込む文体。気づくと読み手は、青いであろうはずの海辺にいざなわれ、沖縄の現実に向き合うことになる。
基地、水質汚染、性暴力、若年出産。キーワードだけでは想像のできない現実が、愛娘との生活を通して語られていく。青い海と空、白い砂浜、眩しい太陽を沖縄の象徴と捉えている者は、波が足をさらうように沖縄の痛みにひきずりこまれ呆然とするであろう。
著者は琉球大学の教授でありながら、沖縄の若者を調査、サポートするライフワークを持つ。沖縄の抱える歴史と政治に翻弄される若者へのインタビューは、ふつうという言葉からは遠く離れた物語のようである。たとえば恋人を性風俗で働かせても心に痛みを感じない青年。父親の暴力から逃げながら少年期を過ごした彼が、ホストで荒稼ぎをしている理由とは何か。事実を知ると読み手の心は、気持ちの置き所がなくなるに違いない。
著者は言う。「東京で暮らしているときに驚いたことのひとつは、軍機の音が聞こえないということだった」「ああ、こんなところで暮らしているひとに、軍隊と隣り合わせで暮らす沖縄の日々のいら立ちを伝えるのは難しいと思い、私は黙り込むようになった」
本土で暮らす人々は、沖縄での出来事をどこか遠くの国のことのよう眺めている。米兵に少少女が強姦された事件、辺野古への基地移設のデモなどの報道が、好奇心を煽るようなものであったことを思い出すとうすら寒くなる。同時に、これまで知らなかった事実の一端に触れ無知の恥にさいなまれるのだ。
夫と幼い娘とともに沖縄で生きる著者。青ではない、赤い海を見つめながら、愛娘が生きることになる未来の沖縄に馳せる思いを受け止めてほしい。
鴻月美里